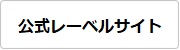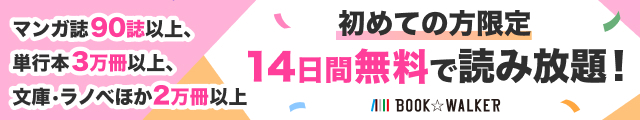- 著者 渡邊 守章
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2025年03月22日
- 判型:
- 文庫判
- ページ数:
- 480
- ISBN:
- 9784044008512
舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで
- 著者 渡邊 守章
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2025年03月22日
- 判型:
- 文庫判
- ページ数:
- 480
- ISBN:
- 9784044008512
理論と実践から東西の舞台芸術の系譜を一望する!
喜怒哀楽を操り、共同体を再生させ、時に神や亡霊をも呼び出す舞台芸術の魅力は如何に生み出されるのか。ギリシア悲劇を範とし、オペラやバレエへと拡散していく西洋演劇史を踏まえつつ、能、文楽、狂言、歌舞伎といった日本の伝統芸能や中国の京劇、バリ島の舞踏も取り上げ、その真髄を鮮やかに描き出す。自らも演出家として活躍した演劇研究の泰斗が、歴史・理論・実作を一本の線で結ぶ入門書の決定版。
解説・平田オリザ
*本書は、1996年に放送大学教育振興会より刊行された『舞台芸術論』を再編集し、改題のうえ文庫化したものです。
【目次】
はじめに
第1章 演劇 この多様なるもの
第2章 劇場の系譜
第3章 劇場とその機構――システムとしての劇場
第4章 演じる者の系譜
第5章 稽古という作業
第6章 劇作の仕組み
第7章 悲劇と運命
第8章 喜劇と道化
第9章 近代劇とその対部――前衛の出現
第10章 東洋演劇の幻惑(一)
第11章 東洋演劇の幻惑(二)
第12章 前衛劇の地平
第13章 理論と実践――世阿弥の思考
第14章 オペラとバレエ――新しいキマイラ
第15章 舞台芸術論の現在
おわりに
解説
参考文献
解説・平田オリザ
*本書は、1996年に放送大学教育振興会より刊行された『舞台芸術論』を再編集し、改題のうえ文庫化したものです。
【目次】
はじめに
第1章 演劇 この多様なるもの
第2章 劇場の系譜
第3章 劇場とその機構――システムとしての劇場
第4章 演じる者の系譜
第5章 稽古という作業
第6章 劇作の仕組み
第7章 悲劇と運命
第8章 喜劇と道化
第9章 近代劇とその対部――前衛の出現
第10章 東洋演劇の幻惑(一)
第11章 東洋演劇の幻惑(二)
第12章 前衛劇の地平
第13章 理論と実践――世阿弥の思考
第14章 オペラとバレエ――新しいキマイラ
第15章 舞台芸術論の現在
おわりに
解説
参考文献
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
もくじ
はじめに
第1章 演劇 この多様なるもの
1 「舞台芸術」と「演劇」
2 さまざまな演劇
3 演劇の多様な局面
4 演劇の四要素
第2章 劇場の系譜
1 ヨーロッパの記憶
2 一九世紀型劇場
3 日本の場合
4 舞台と客席――劇場についての問い
第3章 劇場とその機構――システムとしての劇場
1 舞台の裏の顔――舞台機構と作業場
2 劇場の表の顔――祝祭装置
第4章 演じる者の系譜
1 再現=代行型演技
2 直接的=身体技
3 演じる者の二重性
4 対比の歴史的な系譜――日本の芸能と西洋演劇
5 現代演劇における戦略
第5章 稽古という作業
1 スタッフとキャスト
2 稽古のプロセス
第6章 劇作の仕組み
1 アリストテレス――劇作の基本要素
2 「未決のなかの形式」――『オイディプース王』
3 五幕構成の公理
4 世阿弥の能作論
第7章 悲劇と運命
1 「英雄」のステータス
2 「起源論」の地平――ギリシア悲劇と御霊信仰
3 情念の悲劇
4 人間の条件の劇
第8章 喜劇と道化
1 「笑うべきもの」と「笑わせる仕掛け」
2 道化の系譜
3 道化の仮面
4 喜劇の呪術性
5 対比構造と変容
第9章 近代劇とその対部――前衛の出現
1 近代劇あるいは同時代風俗劇
2 前衛の出現
3 「演出家」の誕生
4 メタ・シアター――演劇についての演劇
第10章 東洋演劇の幻惑(一)
1 一八八九年パリ万国博覧会
2 中国演劇の登場
3 クローデルと日本
第11章 東洋演劇の幻惑(二)
1 バリ島の舞踏とアルトーの「残酷演劇」
2 東洋のレッスン
3 身体性の地平
第12章 前衛劇の地平
1 ブレヒトとアルトー
2 不条理劇
3 「六八年型」演劇
4 古典の読み直し
第13章 理論と実践――世阿弥の思考
1 演劇論としての世阿弥の伝書
2 世阿弥の稽古論
3 花と幽玄――演能の本質
4 幽玄の達成
第14章 オペラとバレエ――新しいキマイラ
1 オペラ
2 バレエ
3 新しいキマイラ――オペラとバレエ
第15章 舞台芸術論の現在
1 再びマラルメの予言について
2 伝統と現代――日本の場合
3 国際交流
4 再びシステムとしての劇場について
おわりに
解説
参考文献
第1章 演劇 この多様なるもの
1 「舞台芸術」と「演劇」
2 さまざまな演劇
3 演劇の多様な局面
4 演劇の四要素
第2章 劇場の系譜
1 ヨーロッパの記憶
2 一九世紀型劇場
3 日本の場合
4 舞台と客席――劇場についての問い
第3章 劇場とその機構――システムとしての劇場
1 舞台の裏の顔――舞台機構と作業場
2 劇場の表の顔――祝祭装置
第4章 演じる者の系譜
1 再現=代行型演技
2 直接的=身体技
3 演じる者の二重性
4 対比の歴史的な系譜――日本の芸能と西洋演劇
5 現代演劇における戦略
第5章 稽古という作業
1 スタッフとキャスト
2 稽古のプロセス
第6章 劇作の仕組み
1 アリストテレス――劇作の基本要素
2 「未決のなかの形式」――『オイディプース王』
3 五幕構成の公理
4 世阿弥の能作論
第7章 悲劇と運命
1 「英雄」のステータス
2 「起源論」の地平――ギリシア悲劇と御霊信仰
3 情念の悲劇
4 人間の条件の劇
第8章 喜劇と道化
1 「笑うべきもの」と「笑わせる仕掛け」
2 道化の系譜
3 道化の仮面
4 喜劇の呪術性
5 対比構造と変容
第9章 近代劇とその対部――前衛の出現
1 近代劇あるいは同時代風俗劇
2 前衛の出現
3 「演出家」の誕生
4 メタ・シアター――演劇についての演劇
第10章 東洋演劇の幻惑(一)
1 一八八九年パリ万国博覧会
2 中国演劇の登場
3 クローデルと日本
第11章 東洋演劇の幻惑(二)
1 バリ島の舞踏とアルトーの「残酷演劇」
2 東洋のレッスン
3 身体性の地平
第12章 前衛劇の地平
1 ブレヒトとアルトー
2 不条理劇
3 「六八年型」演劇
4 古典の読み直し
第13章 理論と実践――世阿弥の思考
1 演劇論としての世阿弥の伝書
2 世阿弥の稽古論
3 花と幽玄――演能の本質
4 幽玄の達成
第14章 オペラとバレエ――新しいキマイラ
1 オペラ
2 バレエ
3 新しいキマイラ――オペラとバレエ
第15章 舞台芸術論の現在
1 再びマラルメの予言について
2 伝統と現代――日本の場合
3 国際交流
4 再びシステムとしての劇場について
おわりに
解説
参考文献
「舞台芸術入門 ギリシア悲劇、伝統芸能から現代劇まで」感想・レビュー
-
日本の文化的な貧困 舞台芸術の多様性 市民の祝祭の場 遠近法を用いた舞台美術 観客との祝祭的な一体感 演出家の意図 体で理解できるまで 幽玄 批判的な視点 笑いは機械的な固さを矯正する 祭りの集団的な行動 心理 …続きを読む2025年04月13日1人がナイス!しています