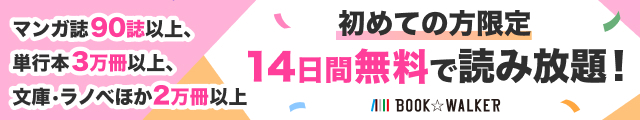- 著 イーサン・モリック
- 訳 久保田 敦子
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2024年12月19日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 320
- ISBN:
- 9784041155271
これからのAI、正しい付き合い方と使い方 「共同知能」と共生するためのヒント
- 著 イーサン・モリック
- 訳 久保田 敦子
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2024年12月19日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 320
- ISBN:
- 9784041155271
AI実用研究の第一人者が贈る、NYタイムズベストセラーリスト掲載作品!
仕事仲間として、家庭教師として、創造性として、コーチとして、そして人として、AIは今後どのように我々の仕事や生活を変えるのか?
本書では、長らく「人工知能」と呼ばれていたAIは、もはや人類の「共同知能(Co-Intelligence)」であるとする著者が、「仕事仲間」「創造性」「コーチ」など役割ごとにAIを捉え直し、まったく新しい関わり方を具体的に提案する。AIが書いた末恐ろしくも圧巻のパートにも注目!
【本書の内容】
・AIは「勤勉な見習いシェフ」
・怖い? 賢い? 怖いくらい賢い?
・AIによる人類滅亡のリスク
・暴走防止のための「ガードレール」の設置と、ガードレールを突破する方法
・AIの巧みな嘘
・AIと協力するためのルール設定
原則1 常にAIを参加させる
原則2 人間参加型(ヒューマン・イン・ザ・ループ)にする
原則3 AIを人間のように扱う(ただし、どんな人間かを伝えておく)
原則4 「今使っているAIは、今後使用するどのAIよりも劣悪だ」と仮定する
・「ソフトウェアのように」ではなく「人間のように」行動する
・AIが見せる「意識のひらめき」
・創造性の自動化
・量を出すのが得意なAIと、駄作を排除するのが得意な人間
・企業やリーダーはAIとどう向き合うべきか
・AIは既存の教え方を破壊する
・宿題の終焉後の世界
・AIの未来についての4つのシナリオ 他
原題:Co-Intelligence: Living and Working with AI
著者:Ethan Mollick
本書では、長らく「人工知能」と呼ばれていたAIは、もはや人類の「共同知能(Co-Intelligence)」であるとする著者が、「仕事仲間」「創造性」「コーチ」など役割ごとにAIを捉え直し、まったく新しい関わり方を具体的に提案する。AIが書いた末恐ろしくも圧巻のパートにも注目!
【本書の内容】
・AIは「勤勉な見習いシェフ」
・怖い? 賢い? 怖いくらい賢い?
・AIによる人類滅亡のリスク
・暴走防止のための「ガードレール」の設置と、ガードレールを突破する方法
・AIの巧みな嘘
・AIと協力するためのルール設定
原則1 常にAIを参加させる
原則2 人間参加型(ヒューマン・イン・ザ・ループ)にする
原則3 AIを人間のように扱う(ただし、どんな人間かを伝えておく)
原則4 「今使っているAIは、今後使用するどのAIよりも劣悪だ」と仮定する
・「ソフトウェアのように」ではなく「人間のように」行動する
・AIが見せる「意識のひらめき」
・創造性の自動化
・量を出すのが得意なAIと、駄作を排除するのが得意な人間
・企業やリーダーはAIとどう向き合うべきか
・AIは既存の教え方を破壊する
・宿題の終焉後の世界
・AIの未来についての4つのシナリオ 他
原題:Co-Intelligence: Living and Working with AI
著者:Ethan Mollick
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
もくじ
プロローグ 3日間の眠れぬ夜
第1章「異星人の心」を創造する
第2章 異星人を人間に適合させる
第3章 「共同知能」についての4つのルール
第4章 「人」としてのAI
第5章 「創造性」としてのAI
第6章 「仕事仲間」としてのAI
第7章 「家庭教師」としてのAI
第8章 「コーチ」としてのAI
第9章 「未来」としてのAI
エピローグ 「私たち」としてのAI
第1章「異星人の心」を創造する
第2章 異星人を人間に適合させる
第3章 「共同知能」についての4つのルール
第4章 「人」としてのAI
第5章 「創造性」としてのAI
第6章 「仕事仲間」としてのAI
第7章 「家庭教師」としてのAI
第8章 「コーチ」としてのAI
第9章 「未来」としてのAI
エピローグ 「私たち」としてのAI
「これからのAI、正しい付き合い方と使い方 「共同知能」と共生するためのヒント」感想・レビュー
-
ヒトが生成AIと共存する方法を論じた本。AIに明確なペルソナを与える、human in the loopで共同知能化する等、他の事例からもよく聞く方法が紹介されている。一方で、生成AIは能力が高い人間にとって成果の向上余地 …続きを読む2025年03月03日7人がナイス!しています
-
日本語版も原著も2024年。大規模言語モデル(LLM)の基本的な仕組み(統計的な計算で文を生成)、仕事や教育にAIをいかに導入するかなどについて論じている。「いかに上手く使うか、付き合うか」がよく論じられてい …続きを読む2025年02月23日4人がナイス!しています
-
OpenAIの創業者が東大で講演した時に、推薦していた本ということで、書店でサクッと購入。本の大きさに比べて文字数はそんなんでもないので、やはりサクッと読めた。かなり穏当なAIの本という印象。大げさなアピール …続きを読む2025年02月09日3人がナイス!しています